目的や目標に対して、まっすぐ進むことは正しい。
果たして本当でしょうか?
何かを学んだり、習得したり、様々なスキルを高めるため、
あるいは何かしらの目的や目標に向かって努力している人、
これからチャレンジしようとしている人は、
どのような方法でそれに向き合うのか。
「正攻法や王道といわれるやり方が、必ずしも目的や目標を達成する最短の道ではない」
私は常々そう思っています。
少々変わり者なのかも知れません。
そもそも、正攻法や王道を否定する時点で、国語的に間違っているような気がしますしね。
(ま、言葉を否定しているワケではないですが・・・)
でも、
「その正論って、少しおかしいんじゃない?」とか、
「そのジョーシキが非常識だよね」とか、
「回り道が正解だった」ということが、
人生では往々にしてあるものじゃないでしょうか。
正論まかり通りがちな現代社会。
でもでも、「そうとは限らない答え」があるのもコレマタ事実。
そんなことを、アレやコレやと考えてみました。
「木に縁りて魚を求む」道は悪くない
いきなりですが、
「木に縁りて魚を求む」という中国の故事をみなさんは知っていますか?
ちなみに、私は知りませんでした。
聞いたことはあるような気もするんですけどね。
言葉のイメージから連想すると「木魚」と何か関係がありそう。
お坊さんがポクポクたたくあの木魚。
きっと、何か仏教に由来するエピソードがあるに違いない。
そう思っていたら、全然カンケーありませんでした・・・。
(なら、書くなよ!)
(;^_^A)
中国の儒学者だか思想家だかに、孟子(もうし)っていう(エライ?)人がいましたよね。
この言葉、孟子が王様に向かって発した言葉から出来た故事なんだそうです。
「木に縁りて魚を求む」は「きによりてうおをもとむ」と読みます。
その意味することは、「木に登って魚を獲ろうとする」ということで、
つまりは「アンタ、それはアホウのすることで、方法としては間違ってますゼ」
ということを言っています。
確かにね。
魚を捕りたければ海か川か湖か、水のあるところに行かないとね。
当たり前と言えば当たり前ですわね。
「手段が間違っていると目的は達成できない」
そういう例えね。
ま、ま、言いたいことはよく分かりました。
でも、これって言葉としての説得力は弱くないですか?
「魚を捕るのに木に登って何が悪い」と言いたくなるのは私だけでしょうかね。
そもそも、これはどういうシチュエーションなのか?
「水がない」とは誰も言っていない以上、木の上から釣り糸を垂れている可能性だってあるワケだし、状況の説明がないと成立しない故事のような気もします。
孟子にケンカを売っているワケじゃありません。
逆に孟子の方からケンカを売っているぐらいの話ですしね。
前述のとおり、この言葉は孟子が王様に向かって発した言葉です。
でも、普通に考えたら、ズイブンと失礼な話だと思いませんか?
「孟子君、王様にケンカ売っとるがな」
誰がどう見ても、どう聞いても、どう捉えてもケンカを売っとる。
ウン。
王様を(暗にアホウだといって)否定していますからね。
「そんなうっすい例えで、よーエラそうに王様にケンカ売ったなー」
と、そこのところだけは感心しますけどもね。
以下、どんな感じで王様にケンカを売ったのか、故事が生まれた時代背景など追いながら、解説してみたいと思います。
究極の選択!!アナタが中華を統一するならどっちを選ぶ!?
A 「武力をもってブイブイと中華を統一する」
B 「徳のある政治をもってジワジワと中華を統一する」
むかーし昔のラジオで「究極の選択」っていう企画がありましたね。
(テレビのキュウキュウじゃないほうのヤツですよ)
ウッチャンナンチャンのオールナイトニッポン
(古い。昭和の話かよっ)
スキだったなぁ
(オモロー過ぎてカードゲームまで買ってしまったもん)
もし、どっちかを食べなくちゃならないなら、どっちを選ぶ!?
A 「カレー味のうん〇」
B 「うん〇味のカレー」
って、いうのはもちろん前フリです。
(脱線してゴメンナサイ)
えと、王様にケンカを売った話でしたね。
その時の時代背景・・・
つまり、故事が生まれた時代背景がどうなっていたのかの確認でした。
時は中国の春秋戦国時代、リアルな漫画「キングダム」の世界です。
(孟子が生きていたのは紀元前372~前289年で、三国志の時代の400~500年ほど前)
当時の中国(=中華)は大小さまざまな国家に分かれていたと言われています。
「秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓」の戦国七雄といわれた七つの大国が有名ですが、それ以外にも中小の国家がたくさんありました。
この時代は中国の歴史の中でも様々な思想や思想家が生まれた時代でもあり、諸子百家の時代とも言われています。儒家、道家、墨家、法家とか、みなさんも聞いたことありますよね。
(ウィキペディア情報だったりしますけど)
儒学の祖である孔子が有名ですが、孟子はその弟子となります。
(ウィキペディア情報だったりしますけど)
孟子のお相手は「斉(=せい)」の王様だとされています。
斉の王様は「武力をもってブイブイと中華を統一する」考えを持っていたそうです。
(究極の選択でいうところの選択肢「A」ですね)
それが健全だとは思いませんが、至極まっとうというか現実的な考えのような気がします。
それに対して、孟子は王様に「木によりて~」とブチかましました。
孟子いわく(以下、想像に私見を加えたフィクション&ノンフィクション)
「民に対する愛こそが全てです。徳のある政治を地道に積み重ねた方が、結局は中華統一を果たすための近道なんですよ。武力でそれを成し遂げるのはアホウがすることです。あなたはアホウですか。違いますよね。ドゥユウアンダァスタン!?」
まあ、そんな感じのニュアンスで王様を詰めて、ケンカふっかけたみたいですよ。
(知らんけど)
まあね。
確かにね。
孟子の言うことは、一見正しいようにも思えますね。
現代の価値感覚からすれば、「武力による政治」よりは「徳のある政治」の方がありがたいし、むしろあたり前の政治のあり方に見えますからね。
でも、当時の価値観からして、それは現実的な提案だったとは思えないんですよね。
まあ、簡単に言って「おとぎ話」ですよ。
現実的でないイマイチな提案。
(そもそも、現代の価値感からしても、おとぎ話であって、武力のない国は隣国から脅威を与えられかねないですからね。当然、「憲法9条があるから平和が維持されている」というのは、日本でしか通用しない「おとぎ話」です)
ま、「おとぎ話」もどうかと思うし、例えもイマイチ。
よくもまぁ、そんな内容で王様にケンカを売ったもんだと、そこだけは感心しますけどね。
ワタクシが王様なら問答無用で孟子をブッタ切ってますけどね。
(イヤ、ブッタ切られても文句言えないような発言でしょうよ)
でも、この逸話が残っているということは、孟子はブッタ切られてはいないんでしょ。
つまり、その時の王様が素直に言うことを聞いたということなんでしょうね。
「斉の王様は度量が大きいというか、先進的な考え方を持っていたんだなぁ」とちょっとだけ感心したのですが、実際には違っていたみたいです。
つまり、孟子のB「徳のある政治をもってジワジワと中華を統一する」という新しい提案に対して、結局、斉の王様は、A「武力をもってブイブイと中華を統一する」という考えを変えなかったみたいなのです。
「何だよ、やっぱりかよ!」
逆に、よくそんな故事が残ったもんだと感心するわ(笑)
ま、斉の王様の「度量が大きかった」というのは間違いない。
斉の王様はエライ。
うん。
(この後、秦に滅ぼされてしまいますけどね)
孟子の説はやっぱりギモン!
こうやって考えると、「やっぱり、孟子ってどうなん?」とギモンを抱いてしまいますよね。学者としての地位を確立させるために、あえてトンデモ説を唱えて、悪目立ちしようと考えていたとか・・・
孟子って人は、性善説を唱えた人でもありますよね。
「人は生まれながらにして善い行いをする性質の生き物である」という説。
人間として希望が持てる話だし、性悪説を唱えられるよりはよっぽど気持ちが良いとワタクシだって思いますが、もしかしたら、この説も当時の中国の人たちからしたら、トンデモ説だったのかも知れませんね。
(何となく、日本人にはしっくりくるけど・・・には、なんて色々と想像すると、やっぱり当時のその地にあってはトンデモ説だったカモ)
ともかくも、孟子は本質的には悪い人ではなかったかも知れませんが、トンデモ説をブチかますことで、自らの地位を確立させようとした人ではなかったのかなと推測・想像します。
(あくまでも、ワタクシ個人の感想ですけどね)
ま、「木によりて魚を求む」の故事を信じるなとは言いません。
ただ、孟子が唱えるトンデモ説の逆張りをすることも決してダメではない。
つまり、正攻法と言われている一般的な方法が、本当の意味での正しい方法なのかどうかは疑ってかかっても悪くないと、ワタクシは言いたいのです。
私たちは神様ではないし、何が正しい方法かだなんて、誰も断定できないハズ。
一人ひとりの人間の特性もみんなバラバラですしね。
個人差というものがある以上、「ただ一つの方法だけが正解である」という説は、もうそれだけでかなり怪しいと考えるべきでしょう。
「木によりて魚を求む」は王道か?
「いいえ、違います」
王道か否かを確かめるには、結局あなた自身がトライ&エラーを繰り返して、あなただけの王道を探求するしかないのです。
モチロン、これもまた1つのトンデモ説。。。
孟子を信じるか、ワタクシのトンデモ説を信じるか。
信じるも信じないもアナタ次第。
やっぱり、究極の選択ってオモロイなぁ
( ´∀` )ヒトゴトナノガイイヨネ


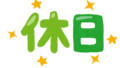
コメント